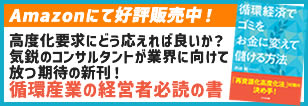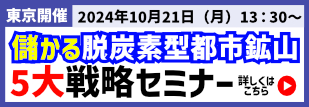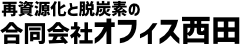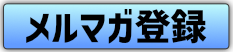「西田さん、世界的企業の担当者だというのに、話題がすごく細かいことばかりだって驚かれたみたいですよ。」先日、日本の某大手企業で環境を担当されている方が国連の担当者と面会した時の様子を伝え聞く機会があり、やっぱりなあ・・と思わされたことがあったので、今日はその話を取り上げます。
21世紀になって2度目の十年紀を終えようとする今日にあって、情報社会や国際経済から見ると、かつてないほど地球は小さくなってきています。日本を別として多くの国では依然として人口増が続き、限りある資源についての懸念が深刻化する流れは一向に変わりません。他方で気候変動や環境汚染の脅威は増すばかり・・という現状について、企業家そしてビジネスマンは何をどう考えれば良いのでしょうか?
私は、「世界観」こそがキーワードだと思っています。特にここ数年、企業を取り巻く経営環境は急激に変化しており、その中で世界観が持つ意味合いが急激に高まっているという変化については押さえておく必要があるでしょう。以下に述べる理由により、その影響は大企業であればあるほど大きく、変化のスピードも速いと言えます。
誤解を恐れずに言ってしまえばこれは2015年にGPIF(年金積立金管理運用独立行政法人)が国連の「責任投資原則」に署名したことに端を発しているというのが私の見方です。これ以降、GPIFの運用資金は社会善に向けたもの「にしか」回らないことになった、と捉えていただいて大枠で間違いありません。
だからどうなの?と言われるかもしれませんが、GPIFが世界最大の機関投資家であることがもたらした金融界への影響はかつてないもので、今も時々刻々と変わり続けているのです。たとえば新規大型案件には必ず気候変動対策に関する情報開示が求められ、働き方改革への具体的なコミットメントは数字で報告することが不可欠になり、統合報告書がBSやPLと同じくらい重要な書類になってきている、というような。
金融が変われば、実業も変わらざるを得ないのです。世界的にはダボス会議やWBCSDなどの枠組みを通して大企業経営者の間に広まった考え方ですが、日本でも特に大企業の経営者レベルにおける問題意識の醸成が進み、矢継ぎ早に対策が講じられようとしています。他方で、長年それでやってきた実業界のストラクチャーは一朝一夕に変われるわけではありません。いまだに「SDGsって何だっけ?」というレベルの中堅幹部は珍しくもなんともないのです。
ところが世界ではすでに、GPIFの先を行くスピードで、社会的課題に適合した新しいビジネスモデルを切り開こうとしている会社があるのです。世界的にはCoca-ColaやUnilever、スノーボードのBurtonなどが知られていますが、いずれもマイケル・ポーターが唱えたCSVなどをバックボーンに、社会善へのコミットメントを強く高く打ち出しています。
具体的な取組みの切り口は途上国への支援だったり、環境対策や社会貢献だったりと様々ですが、いずれも①社会善に対する自社の考え方が哲学として社員に共有されている、②収益を二の次にせず、しっかり儲ける仕組みが出来ている、③他者との協力について基本的にオープンである、などの特徴を備えています。
冒頭で話に出た「大企業の担当者と国連の環境担当者との接点」みたいな話も、当の日本企業にとっておそらくは矢継ぎ早に講じられた施策の一端ではなかったかと言うのが私の洞察です。これまでの展開ではおそらく出会うことすらなかった方々が会っただけでも大きな前進、と言う見方があるかもしれません。ただ、あるいは準備ができたとは言い難い状況だったとすると、その結果として明らかになったのが「Coca-Colaとはあまりに違う日本企業の現実」で、国連担当者の失望を誘ったとするならば、却って逆効果だったのではないでしょうか。
まずは、経営者が哲学として信ずる世界観を社員と共有するところから始めてください。そのうえで、実践を通じて哲学が社内に浸透するよう時間をかけることです。そして「結局は上滑りなスローガン」、で終わることのないように、最後までしっかりと目配りをすることです。最近よく聞くようになったSDGs(国連の「持続可能な開発目標」)を指標として取り上げるのは悪くないのですが、共通言語として社会に行き渡っている分だけ「やってるふり」と批判されることのないよう、くれぐれも覚悟を決めて実施してください。
企業の評価は世界観で決まる、もしかするとそんな時代がもうすぐそばまでやってきているのかもしれません。