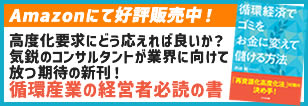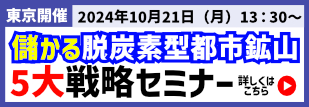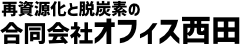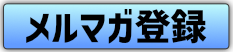先日の台風15号は千葉県南部に甚大な被害をもたらしましたが、それによって発生した災害がれきの処理が大きな負荷になっていることが一部で報道されています。新聞報道によると、自治体の焼却工場はOB人材の応援も受けて、24時間操業によるフル稼働体制で災害がれきの処理を続け、周辺自治体の協力も得て災害がれきの処理に当たったそうです。
環境省は2014年に全国の自治体に対して「災害廃棄物処理計画」作成を求めており、この計画が国の「廃棄物処理施設整備計画」に反映される仕組みを構築しています(災害廃棄物対策指針の位置づけ及び構成 https://www.env.go.jp/recycle/waste/disaster/guideline/ による)。
通常、焼却工場など自治体が所管する一般廃棄物(家庭や事業所から排出される、いわゆる一般ごみ)処理施設については、想定されるごみの排出量を一日16時間程度の稼働で無理なく焼却できる容量で設計されています。大規模な自治体では、人口減少に加えて環境教育の充実などから実際の排出量が設計値を下回り、平時の操業について容量のゆとりが生じている場合もありますが、一旦災害が起きると発生するがれきの量は尋常ではありません。2016年の熊本地震では約310万トン、2018年の西日本豪雨では約180万トンの災害がれきが発生したと言われています。
これらの災害がれきをどう処理するか、という問題ももちろんありますが、環境ビジネスの視点から言うと、災害レジリエンス(抵抗力)を強化してがれきの発生量を減らすことにこそビジネスチャンスがあるのではないかと思われます。
最近、自宅近くに新築のアパートが出来たのですが、窓という窓にシャッターがついています。他方で中古の集合住宅にはガラス窓の保護が不十分な物件も少なくないのですが、窓ガラスにワイヤーが入ったサッシや、後付けできるタイプのシャッターなどの対策ビジネスにとっては商機であるということができるでしょう。同様に、エアコンの室外機や太陽光発電パネルのパワコンなどを水没から守るためのかさ上げ架台なども需要が高まるのではないかと思われます。
そして何より千葉の経験を生かすのが「停電対策」です。緊急避難的な対策としては、自動車の12V電源を家庭用電源として使えるインバーターを備えておくことでしょう。小型の発電機があればそれに越したことはありませんが、家庭で太陽光発電をされている場合、バッテリーの備えがあるだけで夜間にも電気が使えるため、蓄積される生活ダメージは全く違ってくるのです。
東日本大震災後には、家具の転倒を予防するためのつっかえ棒などがよく売れたことが思い出されます。まさにビジネスチャンスは正直です。今のところ気候変動による災害の深刻化が向こう数年以上は続くものと思われます。災い転じて福となせるよう、感応度を研ぎ澄ませておきたいものですね。