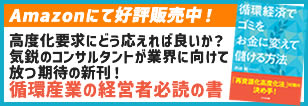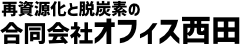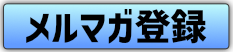英語だとHuman resourcesと呼ばれる人的資源は、日本語では一般的に人材と言われています。資源も材も、消費されるイメージの強い言葉だと思います。専門用語だと「経営資源の配分」だとか、「人材配置」という言われ方もしますが、それこそますます人をモノと同列に論じる考え方が強く出てきてしまいます。
他方で特に日本の資源循環ビジネスでは、有害物質など難しい対象物を扱う事業特性から、歴史的に「信頼できる人とでないとビジネスをしない」という風土が養われてきました。常にフェイストゥフェイスの関係を重んじ、良い意味で現場中心主義を貫いてきたところがあります。確かに法規制もありましたが、このような考え方は商圏が小さく固めるために役立ったようにも感じます。伝統的に「企業は人」「商売は人」という考え方で成り立ってきた、というわけです。
しかしここ最近では、経営の近代化が言われる中で、「人に仕事をつける」のではなく「仕事に人をつける」ことで最適配置を実現するという考え方のほうが主流になってきています。資材や時間・スペースなどの投入資源を可視化し、人もまた最適配置を考えることで効率を上げてゆく、という仕組み自体に間違いはありません。ただその取り組みが進んで仕組み作りが先行すると、仕組み以上の効果をもたらすことが期待しづらくなってくる、という変化もみられるようです。システムの硬直化が組織のダイナミズムを奪ってしまう、というような変化です。これは何に起因するのでしょうか?
「言ってることはわかるが、規則のやり方と違う」「この変更を認めると、他も変更に対応しなければならない」「これまでにそんなことをした実績はない」このような発言が中間管理職から聞かれるようになったら要注意です。いずれもシステムの硬直化が進んだ組織でよく聞かれるもので、仕組みを動かすべき人材がボトルネックになっていることを如実に示しています(岩盤化、とでも言うべき変化の始まりだと思っています)。
規制に縛られているとどうしても仕事の仕方が硬直化しがちになるのは仕方ないとして、それを打破するのはやはり人材に負うところが大きいのです。ポイントは、そういうインセンティブが働いているかどうか、という点にかかってきます。
現場に入り、人対人のコミュニケーションから問題の本質を発見し解決して行く。この力こそが売り上げそして利益を生み出す源泉になっています。それは経営の近代化が進む前でも後でも基本的には変わりません。まさに人「財」と呼ばれる所以がここにあります。仕組みづくりを進めるのと並行して、人「財」を手当てしないと片手落ちになってしまうというわけです。
仕事の仕組み化はどんどん進めましょう。他方で人「財」を大切にする経営を堅持することで、仕組みが自律的に回るように仕向けてゆくこと。企業の発展性を約束されたものにするためには、これ以外の道はないのです。