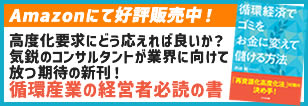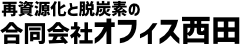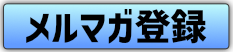突然ですが、あなたは日本社会が規律性に富んだ社会だと思いますか?私は海外から日本に戻ってくるたびに、社会の規律性について考えさせられることが多いです。
たとえば、朝の通勤電車を待つ駅のホームの行列は見事なまでに規律の取れた動きを示します。そうかと思うと、優先席で寝ている若者が老人に席を譲らないというシーンもまた、日常よくある場面だと思います。小学生は手を挙げて横断歩道を渡っていますが、子供を乗せたママチャリが車道の右側を逆走していたりします。
一般家庭にゴミの分別を徹底させているのは立派だと思う反面で、海洋プラスチックごみは日本の周辺にすごく多いという情報もあります。一体それがどのようにして投棄されたのか、近頃レストランなどで進んでいる脱プラスチックの取り組みはどれくらい実効性のあるものなのか、ちょっとよくわからないと思うのは私だけではないと思います。
環境問題について役所の言うことが良く守られている、と言う意味において日本は規律ある社会だと言い切ってしまって問題ないと私は思っていますが、実は海外はそうでなかったりします。特に途上国ではその悩みが深く、法令違反あたりまえ、違法投棄もごくふつう、そこでどうやって規律を徹底させてゆくのか?という課題は、環境ビジネスの海外進出にとって避けて通れない重要なものです。
私が提案するソリューションの一つが「教育」です。日本も一世代前までは、分別が徹底されないなどという事例に溢れていたと思います。時間はかかりますが、反面で着実な成果が見込めるので、教育をどのように取り上げるのかについてはぜひともご検討をいただきたいと考えます。
今一つは、前回お話しした「ソフトロー」による柔らかな規制が考えられます。ISOによる基準認証だとか資格制度などがこれに当たるわけですが、得られるメリットに十分魅力があれば、これを梃子に使った行動変容は比較的進めやすいものになると言えます。
そのうえで、やはり何と言っても決定打は法律などによる「規制」です。それがスムースに生かせるようになるためにも、「教育」「ソフトロー」との組み合わせで実施されるのが理想的なのですが、どうすれば途上国社会に対して効果的な働きかけができるのか?どのような「規制」が望ましいのか?などのような視点から、当社では環境ビジネスの海外進出をサポートするための行政対応法をアドバイスしています。「教育」「ソフトロー」「規制」の三点セットで考えることができると、規律ある良い社会への青写真も描きやすくなりますので、ぜひ一度御検討ください。